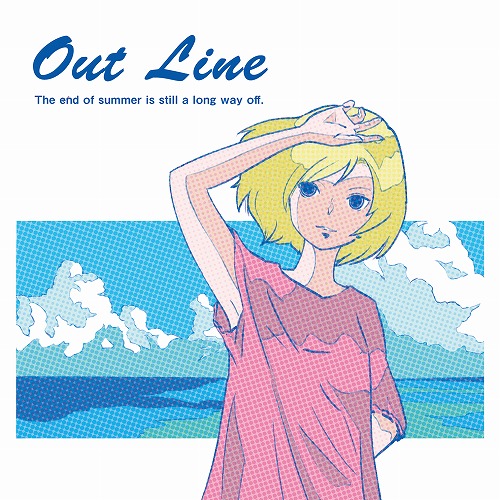| <<2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2026>> |









かたまりたけし -塊魂Tribute Original Sound Track- / Namco, Columbia(COCX-35745-6)
2004年にPlayStation 2用ゲームとしてNamco(現在のBandai Namco Entertainment)より発売、以降Nintendo Switch、PlayStation 4、 XBox Oneなどにもシリーズ展開された転がり型アクションゲーム「塊魂(かたまりだましい)」のトリビュート・アルバム。 2009年8月、2枚組としてリリースされた。ゲーム中で使用された音楽を中心に、国内外のアーティストが参加する豪華なアルバムとしてゲームファンのみならず音楽ファンからも注目を集める話題作。 先日ついに音楽配信が始まったそうだが、へそ曲がりな亭主、CD版(もちろん新品)を購入した。Disc 1、Disc 2にそれぞれ18曲、全36曲を収録。
参加アーティストを収録順に挙げていくと、大橋卓弥(スキマスイッチ)、Saigenji、GUIRO、AFRA、Buffalo Daughter、堀越高等学校吹奏楽団、キリンジ、Beautiful Hummingbird、 ゆうさま&なつこはん、SOFT、松崎しげる、Senor Coconuts、YMCK、Leah Dizon、松前公高、Atom、Micazo、王様ロボ、レオパルドン、レイ・ハラカミ、SEXY-SYHTHESIZER、Hardfloor。 国内から国外、メジャーからインディーズ、吹奏楽からJ-Pop、チップチューン、ラップ、テクノまでおおよそ考え得るすべてのジャンルのサウンドが2枚のアルバムに凝縮されている。 ここまでバラエティ豊かなのにアルバムとして成立するのは各曲がゲーム内で使用されているため、そしてアレンジに際して各曲のメロディやリフをしっかり用いているためだ。 ゲーム中のBGMにはヴォーカルが入っているとのことなので、ゲームの雰囲気そのままのアルバムに仕上がっているようである。 なおレイ・ハラカミ氏は2011年に逝去していて、聴いていると彼が今でも音楽活動を続けているように思える。 各曲の間にはNamcoのサウンドチームから三宅優氏によるちょっとしたショート・ソングが挟まっていたりするので、常にテンション爆上げ、という感じではなくよい感じに緩急がある。 全体的にはハッピーな雰囲気に仕上がっているので、肩肘はらずゆったりと聴くことができる。
ところで亭主は「塊魂」をプレイしたことがなく、動画サイトなどでゲーム画面などをみてもプレイしたいと思ったことがないので、本アルバムがどれだけゲームの雰囲気を表しているのか、 またどれだけ外しているのかの度合いがよくわかっていない。 先にも「ゲーム中のBGMにはヴォーカルが入っているようで」と伝聞調で書いた後「ハテ」と思って動画サイトでゲーム実況を確認したのだが、予想以上にぶっとんでいるというか、 アルバムよりもさらにアヴァンギャルドなことに驚いた。おそらくゲーム画面の妙なテンションに引っ張られてのことなのだろうがーーー。 個人的にはアルバムだけでも充分かな、とちょっと引き気味にとらえている(2025.03.19)









Two Moon / Tomoo, Pony Canyon(PCCA-06223)
東京都出身。Youtube、ライブを中心に活動するシンガーソングライター・TOMOOさんの1stフルアルバム。2023年、Pony Canyonよりリリースされた。 インディーズ時代の楽曲でYoutubeを中心に大ブレイクした"Ginger"ほか、ドラマ・映画主題曲を含む全13曲。
"Ginger"がYoutubeで500万再生を記録、ラジオでヘビー・ローテーションされたことをきっかけに、ネクスト・ブレイク・アーティストとして注目を集めるTOMOOさん。 アルバム1曲目の"Super Ball"のMVは677万再生、同じくアルバム収録の「オセロ」が221万再生とヒットを叩き出している。 特徴的なロー・トーンと、シリアスな歌詞から紡ぎ出される独特の世界観にはまる人は多いようで、かく言う亭主もインディーズ時代からずっと注目している。 アルバムは前半は比較的明るめのキャッチーな曲、後半はドラマ「ソロ活女子のススメ3」テーマ曲「夢はさめても」、 映画「君は放課後インソムニア」主題歌「夜明けの君へ」など有名曲を含めつつディープな曲を集めている。
「生」をまっすぐに見つめる歌詞、キャッチーだが決して軽くないメロディラインとアレンジは聴くほどに心に迫るものがあって、昨今流行のポップ・ミュージックと少し趣が異なる。 ただ、Youtubeで彼女の音楽を聴き、またラジオなどで彼女の曲をリクエストする人たち(そして亭主もその一人だ)にとって、彼女のサウンドは救いでもある。 「シリアス」だが迷いがなく、現実から目を逸らすことなく信念を貫き通そうとする歌詞、そして意思を感じる歌い方に、多くの人が勇気をもらっていることだろう。 このレビューを書くにあたり彼女の音楽はどんなジャンルに分類されるだろうと考えて、往年のフォーク・ミュージック(たとえば吉田拓郎や井上陽水)を思い出したのだけれど、 あらためて彼女の曲を聴くとそのどれとも異なっていることに気づく。 彼女の音楽は誰とも戦わず、誰も批判せず、かといって現状に甘んじたり、弱音を吐いたりすることもない。ただ自分の進むべき道を見据え、現在進行形で歩を進めている。 インディーズというアンダーグラウンドな時代を経て、どうすればこんな曲が書けるのだろうと不思議で仕方がないのだが、前に進もうとする意志の強さこそが、 彼女の音楽が多くの人に支持される理由なのだろう。
メロディやリズムには外国のポップ・ミュージックの影響が感じられ、ディープな曲にはブルーズの、ポップな曲にはオールド・アメリカン・ポップスの手法が使われているあたりも興味深い。 もちろんポップ・ミュージックずばりではなく彼女の弾くピアノのはしばしにテイストが感じられるという程度なのだけれど(2025.03.19)









Out Line - the end of summer is still a long way off. / Nakamura (YMCK)
チップチューン・バンドYMCKでは作曲とVJを担当。Youtubeでは毎回「濃い」レトロゲームの話題を配信するNakamura氏による自主制作のアルバム。 SEGAの体感ドライブゲーム"Out Run"の楽曲にインスパイアされた、夏をイメージさせる爽快なドライビング・ミュージック。全4曲。 なお本アルバムはBEEP通販で購入した。いわゆる「製品番号」や「レコード会社」の表記が一切ないため市場に流通する量は極めて少ないモノと思われる。
Out Lineというタイトルがまずもってアウトランのオマージュであることは間違いなく、楽曲数もアウトランの楽曲数と同じ。 4分超の楽曲3曲に、2分の楽曲1曲(アウトランではネームエントリの際に流れる曲)、という構成も、また各曲のアレンジもアウトラン収録の音楽と共通している点も、とにかく「アウトラン」を意識している。 M1「忘れられない夏 (Song nameing by Mizutama)」のラテンなイントロといい、M2"Along The Coast"のフュージョンなイントロといい、 曲の入りまでしっかりと原曲に似せているので、アウトランの楽曲をよく知る人ならば「あ、これはあの曲だな」とすぐさま気が付くに違いない。 さらに言えば音源もしっかりとオリジナルに似せており、特にリズム・セクションのドラムの音色は、SEGAのADPCM音源のそれとそっくり。 今の時代にあえて過去の音源を使うあたりがこだわりなのだが、知る人ぞ知る、といった感じなのが非常に心地よい。アウトランのファンによる、ファンのためのアルバムといったところだろうか。
なお曲数4曲、アルバム長15分というのは個人的には少し物足りない。もうちょっと聴いていたい、聴いていたいけどすぐ終わってしまうので繰り返し聴きたい、と本当にエンドレスに楽しんでいるのだが、 できればもう1曲、メガドライブ版アウトラン収録の"Step on the Beat"をボーナストラックに含めてくれていたりするとさらに嬉しかったかもしれない。
ジャケットイラストのとおり、またアウトランと同じく、夏のドライブのお供にうってつけの爽快なアルバム(2025.03.12)









音楽列車 / World Standard, MIDI Creative(CXCA-1322)
音楽家、文筆家として活動する鈴木惣一朗氏のソロ・プロジェクト、World Standardのアルバム。 1982年から1984年にカセット・テープでのみリリースした、メジャー・デビュー前のアルバム3部作の3作目が本作となる。 楽曲の一部は1985年にノンスタンダード・レーベルからアルバム「ワールド・スタンダード」として発表されている。アルバム未収録曲を含む全10曲。
女声によるスキャットをメインに、歌曲や童謡をイメージさせる楽曲を多く集めた第3作目。全体的に明るい、牧歌的なサウンドは「音楽列車」のタイトルにふさわしい。 一方で民族音楽(たとえばロマや東欧の音楽)やミニマル・ミュージックの手法を積極的に取り入れていて、 当時としてもかなり変わった(というか商業音楽としてテレビやラジオで流れるにはあまりに異質な)サウンドに仕上がっている。 この前のレビューにも書いたが亭主はアルバム「ワールド・スタンダード」で本アルバム収録の曲を何曲か聴いていて、時代にそぐわない音楽だな、という印象を受けていた。 そうそう、当時おつき合いしていた女性も本アルバムを聴いてくすくすと笑っていたのを思い出した。 あらゆる音楽がネット上に等しく存在する現状にあっては「こういうのもあり」という評価になりそうだが、少なくともアルバムリリース当時、この音楽がしっくりくるシーンはなかったように思う。 渋谷あたりのお洒落な雑貨店や、アパレルショップや、パルコや109あたりでBGMとして使われたのだろうか。よくわからない。
もう一つ、このアルバムを聴いていて、戸田誠司さんが所属していたインストバンド「リアル・フィッシュ」を思い出した。 なかでもアルバム"The Very Big Band In Heaven"は亭主が一番好きな、そして学生時代よく聴いたアルバムだったのだけれど、 このアルバムもまた「ワールド・スタンダード」と同じくジャンル分けが難しい、強いていえば「インスト」や「イージーリスニング」に分類してそのまま放置される、 そんなアルバムだったと記憶している(あるいはとりあえず「日本のアーティスト」の棚に置かれて忘れ去られてしまうか)。 いやいや、そんなノンジャンルな、不憫な音楽はほかにもあったはずだぞ、と古い記憶がどんどんとよみがえってくる。 YMOの散開以降、日本に再びテクノの潮流が現れるまでの間、進むべき道を見失った亭主はこのあたりの音楽をひたすら掘っていたはずだ。 自室のレコ棚を漁ればこのあたりのアルバムはいくらでも出てくるはずだーーー。
あらゆる音楽がネット上に等しく存在する現在にあっても位置づけの難しい、しかし亭主にとってはYMO以降の音楽シーンを補間する思い出深いアルバム(2025.03.10)









Yoimono / World Standard, MIDI Creative(CXCA-1321)
音楽家、文筆家として活動する鈴木惣一朗氏のソロ・プロジェクト、World Standardのアルバム。 1982年から1984年にカセット・テープでのみリリースした、メジャー・デビュー前のアルバム3部作の2作目が本作となる。 楽曲の一部は1985年にノンスタンダード・レーベルからアルバム「ワールド・スタンダード」として発表されている。アルバム未収録曲を含む全10曲。
生楽器をフィーチャーし、ミニマルやカントリーの要素を取り入れた"Asagao"に対して、ポピュラー・ミュージックやイージーリスニングの要素を強めた本作。 ヴォーカル、ヴォイスが多用されており、一聴するとモンド・ミュージック的な作風も感じられる。 いわゆるJ-Popのサウンドではなく、音楽劇を思わせるアレンジが施されているので、聴く人によっては童謡のように、また往年の青春歌謡のように受け取られるかもしれない。 かく言う亭主も学生時代にこのアルバムの楽曲が収録されたアルバム「ワールド・スタンダード」を聴いて相当こっぱずかしかった、というか、場違いな印象を受けていた。 少なくともテクノやシンセポップを聴くようには聴けなかった。 動揺を隠しつつ「まあこんなのもあるよね」と記憶の中にとどめておくのが精一杯だったのだが、まさかあらためて今、これを聴くことになるとは。
アルバム"Asagao"でも書いたことだが、その曲調にはペンギン・カフェ・オーケストラや、マヘル・シャラル・ハシ・バズとも共通する手作り感・素朴さがあるものの、 楽曲としての完成度は非常に高く、手作り感もまた「狙った」ものと思われる。 多くのアーティストを起用しつつ、一つの作品へと練り上げていく鈴木氏のプロデュース力、また様々な音楽ジャンルを引用しつつ決して時流に流されない意志の強さに驚きつつ、 いやこれってデビュー前のアルバムだよね、と改めて氏の音楽知識の深さに驚かされた(2025.03.10)









Asagao / World Standard, MIDI Creative(CXCA-1320)
近年は細野さんとの対談本でも有名。音楽家、文筆家として活躍中の鈴木惣一朗氏のソロ・プロジェクト、World Standardのアルバム。 1982年から1984年にカセット・テープでのみリリースした、メジャー・デビュー前のアルバム3作が本作シリーズとなる。 なお楽曲の一部は1985年にノンスタンダード・レーベルからアルバム「ワールド・スタンダード」として発表され、また後年未発表曲含めた2枚組とアルバムとして再発されているので、 部分的に聴いたことのある人は多いと思われる。
なお、アルバム「ワールド・スタンダード」を最初に聴いている亭主にとっては、今回リリースされた3枚で1枚のアルバム、という印象が強く、 3枚を別々にレビューすることはなかなか厳しいのだけれど、せっかくなので1枚ごとにレビューを試みる。
アルバム"Asagao"には「麦秋」「夜会(ソワレ)」「カナリヤ」ほか全11曲を収録する。 ギターやアコーディオンなど生楽器によるオーガニックな楽曲、ミニマル・ミュージックとカントリー・ウェスタン、それに民族音楽を掛け合わせた構成に、懐かしさと新しさを感じさせる。 その後鈴木氏はカントリー・ミュージックをフィーチャーした名作"Country Gazette"を1997年にリリースするのだが、本作からすでに構想があったかのもしれない。 演奏の背後になにやらざわざわとした話し声が収録されているのは演出だろうか。 単なる「音楽集」を越えて、映画のサウンドトラック的なストーリーを感じさせる。 手作り感のある素朴な曲調は、ペンギン・カフェ・オーケストラと共通するものがあるだろうか。 アルバム「ワールド・スタンダード」を聴いた時には漠然としか感じられなかった本作の個性が、3部作となった瞬間にじわりと染み出してきた感じでもある(2025.03.10)